業務分野ワークライフバランス研究所
従来の「働き方の意識」を変える「制度の再構築」をし、経営戦略としてのWLBを実現しませんか?
昨今は人口減少による人材不足や2019年4月からの働き方改革関連法案が施行され、経営戦略としてのワークライフバランス(私生活と仕事の調和)は必要不可欠な時代です。当社ではワークライフバランス施策を成功させる要素として「退職させない(しなくてもよい」職場環境の構築」を重視し、「短い時間でも成果が出せる仕事の仕方」 「出産、育児という時期においても働き続けることが出来る」 「父親・母親としての自分と仕事を両立できる」為の諸制度を構築するサポートをいたします。社会保険労務士としてたくさんのクライアント企業と共に数々の労務コンサルティングを行ってきた経験で時代とニーズに合った最善のご提案が出来ると考えております。


こんなお悩み解決します
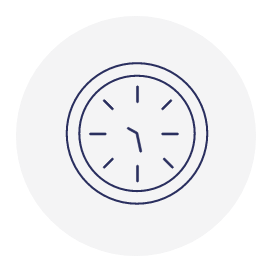 長時間労働が常態化している。
長時間労働が常態化している。
徐々に是正する手順が知りたい。 多様な働き方を認めて、人材不足を
多様な働き方を認めて、人材不足を
解決したい。 ハラスメントの窓口は
ハラスメントの窓口は
設置したものの、実際に起こったときの対応に不安がある。
サービス特徴
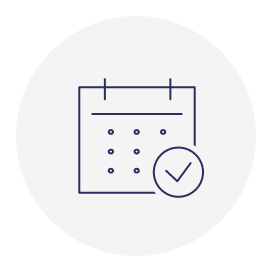
週休3日勤務制度・短時間正社員制度導入サポート
休日を増やすことや短時間での勤務は育児や介護と仕事の両立を可能とし、育児や介護を理由とした離職を防止できます。さらに近年では、柔軟な働き方、多様な働き方のニーズが高まっており、こういった制度を選択できることはワークライフバランスの実現につながります。

LGBT対応規定の作成、企業セミナー
LGBTとは、セクシュアルマイノリティ(「性的少数者」ともいわれます)を表す総称として使用されている表現です。日本におけるLGBT層の割合は8.9%(電通調査2019)に上り、日本にいる左利きの人の割合とほぼ同じです。LGBT社員に対し、不利益な差別的言動および取扱をしないような制度をつくり、意識改革や風土醸成のための啓蒙活動を行う取組みを行います。また、LGBT対策の企業セミナーも対応可能です。
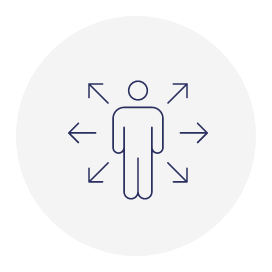
限定社員制度導入サポート
地域限定社員や短時間正社員等、育児や介護の事情で転勤が難しい者等について、就業機会の付与と継続を可能とする新たな形態の社員制度が登場しましたが、近年では働き方へのニーズの多様化が進み、「希望する地域で将来のキャリア展望を描きたい」「仕事に関する資格を取るために学校に通いたい」等の声も聞かれます。このような多様なニーズに合った制度の導入をご提案いたします。

ハラスメント相談窓口サービス
2022年4月より、中小企業もパワーハラスメントの防止対策が義務となりました。何か起こった場合は損害賠償責任が問われる可能性があります。この義務の中に、「相談窓口の設置」がありますが、社内相談窓口においては、知識不足により対応が難しい、担当者の教育に時間がかかる等の相談を多く受けます。当社ではそのようなお悩みを解決するために、外部相談窓口サービスをしております。

ハラスメント相談窓口研修サービス
ハラスメントの防止対策の義務の中に、「相談窓口の設置」がありますが、当社の外部相談窓口サービスの利用の他に、窓口担当者向けの研修サービスもございます。その他各種ハラスメントに対しての研修サービスもあります。また必要に応じて、従業員への配布用ハラスメント冊子の作成も行っております。

SDGs対応規定の作成
SDGsとは、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。会社としてSDGsに対応した規定を作成することは、社会貢献であり、社員満足度にもつながります。

カウンセリングサービス
ハラスメントの被害者に対するもの、ハラスメントの第三者に対するもの、その他メンタルヘルスに不安を抱える方に対するもの等がございます。当社のような外部に依頼することで、安心感もあり、また資格を持ち、経験の豊富なカウンセラーが対応するので、適切なケアやハラスメントの解決へのお手伝い、快方へのサポートが可能です。また定期的に月1~2回(1日~半日)企業にお伺いしてカウンセリングを行うサービスもございます。
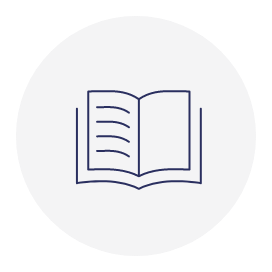
出産制度、育児休業ハンドブック(従業員用・管理職用)作成サポート
産休、育休に入る前の社員から、「どのような制度があるかわからない」という不安の声がありませんか?従業員の不安を解消し、安心して働き続けるサポートとして従業員ハンドブックの作成が効果的です。(法律上、2022年4月1日から労働者もしくは配偶者が妊娠又は出産の申出があった場合、個別の周知の措置は義務となりました)また、管理職や人事担当者用の管理職用も作成を行っております。
その他対応業務
- 在宅勤務制度導入サポート
- 副業・兼業対応規定の作成
- 65歳定年制度導入サポート
- 妊娠出産、配偶者の転勤に伴う再雇用制度導入サポート
- くるみん取得サポート
- フレックスタイム制度、インターバル勤務制度、時差出勤制度、導入サポート
- 時間単位有給/積立保存休暇 導入サポート
- 助成金指導
- 企業内研修・休職者復帰支援サービス
サービス導入までの流れ
※サービスにより流れが変わりますので、以下は一例です。- STEP当HPの「お問い合わせ」フォームよりご連絡下さい。
お問い合わせ頂いたら打ち合わせを実施します。オンライン、ご来社どちらでも対応可能です。 - STEP打ち合わせで現在のワークライフバランス施策等についてお悩みや疑問に感じているところについて伺い、最適な制度や規定変更等の方向性を固めます。※貴社のワークライフバランス施策の歴史やお考え、新しい制度や規定の適用タイミング等についてお聞かせ下さい。
- STEP打ち合わせの内容に基づいてお見積りと全体的なスケジュール、今後の検討項目をご提示します。ご確認頂いたらスタートです。
- STEP例えば新しい制度適用の場合、まず弊社で規程案を作成して打ち合わせを実施します。打ち合わせでは規定の条文について、内容や意味するところをご説明します。※打ち合わせの回数は内容により変わります。研修等のサービスの場合はその説明する会を設けます。
- STEP次回の打ち合わせまでに、直近のミーティングでの検討・確認事項について貴社で議論・方向性を確定させて下さい。弊社はミーティングにて確定した内容を規程案等に反映させます。
よくあるご質問
-

研修はどのような講師が担当されるのでしょうか?
企業研修の実績が多数ある、外部コンサルタントの講師が担当します。詳細はから確認できます。
http://www.tk-sr.jp/pick_up/training/ -

ハラスメントの研修にはどのような種類がありますか?
窓口担当者が実際に相談を受けた時の対応の研修や、管理職向けの研修、従業員向けの研修等、ニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。
-

出産制度、育児休業ハンドブックというのはどのようなものですか?
その企業の就業規則および育児介護休業規程の内容をわかりやすく紹介し、従業員用はどのような手続きが必要なのか等が明確になっております。管理職用は法律や企業規定に沿って、従業員に対して何をする必要があるのか、何を配慮するのか等が明確になっており、多くの企業にご好評いただいております。
-

フレックスタイム制度を導入してはどうかと役員から言われています。フレックスタイムの導入方法がわからず困っています。
フレックスタイム制が合う職種と合わない職種があると当社は考えておりますので、貴社の現状の課題をお聞きした上で、フレックスタイム制と他の勤務制度を含めて課題を解決できる制度をご提案いたします。
-

社内にLGBTの社員がいるかどうかわかりません。規定を作成しても該当者がいない場合は意味がないのではないかと思っています。
LGBTの当事者はカミングアウトをすることを避けており、カミングアウトした後の不利益な差別行動を懸念しております。企業側がカミングアウトしやすい環境を作りが先であると考えます。企業としての方針を具体的に明記し、社内外へ発信することが肝要となります。





